Amazon.co.jp
改めて、障害福祉について学ぼうと思って読んでみました。
本の感想というより、読んだことによって感じたことを綴るので本からは逸れていくかもしれません。
まずすっきりしたことは、障害は障害を持っていることではなく社会の障壁により生ずる、という考え方の名称が「社会モデル」と分かったことです。
名称が分かったほうが説明が楽ですから。
それより驚いたことは「優生保護法」が1996年まで存在していたことです。
厳密には1996年に「母体保護法」に改正されたのですが。
ずっと昔の話だと思っていました。
さて、この本では世界的にみる障害者への対応の歴史が書かれており、様々な条約が出てきますが、
どうやら日本は条約に批准するのがいつもかなり遅いです。
ただここで面白いと思うのが、外国の方が日本に来て驚く、感心することのひとつにバリアフリー化があげられます。
点字ブロックは日本発祥らしいですし、車いすの方の電車の乗降時の折り畳み式スロープ?はもとより、
降りる駅の車両のところで駅員さんが待機しているのには私も驚きました。
どうなんでしょう。日本人は法を順守する気持ちが強いのか?枠組みが設定されさえすれば、その枠組みにそい、その中で工夫、改善をするということが得意なのでしょうか。
私は後者だと思います。そもそも法律なんてどんなものがあるかもわからないのですから。
(例えば、「障害者差別解消法」なんて誰が知っているのでしょう?まあ、義務化の部分があるので事業主とかは把握しているのでしょうが。)
ただ、バリアフリーなどはハード面ですよね。ソフト面というのかわかりませんが、人間関係、心の在り方とかそちらはなかなか難しいですね。
社会生活の中での差別とか。もちろんなんでもかんでも平等に同じことができて当たり前、というのも違います。差別と区別は違います。また逆差別もおかしな話です。
本来的には集団の話のようですが、集団は個人の集まりなので、やっぱり心の在り方ですよね。
そして、福祉の現場でもなかなか問題は多いようです。福祉事業所、介護施設、病院などでの虐待のニュースが流れてきます。事件として取り上げられることがあるということは、事件になっていない事案が少なくないのだと思います。
人と直接かかわる仕事というのはとても難しい仕事だと思います。体を支える、器具を使う、などの技術面はある程度学んだり、慣れたりということが可能なのでしょう。しかしそれ以外の部分の気を配る、心を通わせるなどは本で学べるものではないです。相手のふとした仕草、目線だったり、声の出し方、呼吸など、とても高度な技…というのか、ある意味センスだと思います。
技術はあるのかもしれないけれど、無遠慮な言葉を投げかける人、無神経な人は存在します。ただ、虐待報告などにもあるように、「やってくれているのだから我慢する、言えない」となってしまい、増長させることになっているようです。
やはり福祉現場(医療、介護含む)で働く人の待遇面をよくして、職種によってはもっと資格の敷居を高くし、質をあげるべきではないかと。
なんだかまとまらなくなってきました。
心の在り方のような部分で、以前から思っていることがあるのでそれはまた別で書きたいと思います。
障害の社会モデル
障害を個人の特性ではなく、おもに社会によって作られらものとみなす考え方。
障害者の生活に不自由があるのは制度的障壁や偏見、社会的廃除のためであるという立場。
しゃかいによって作られた制約に着目し、障害者のニーズに対して公平な社会的・構造的支援が提供されているかどうかを問題にする。
障害の医学モデル
障害を個人の問題としてとらえ、心身の機能を「正常」に近づけることで回復を目指すべきと考える。
―Wikipedia
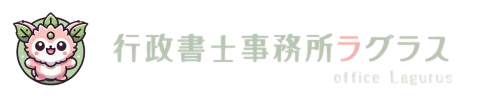



コメント